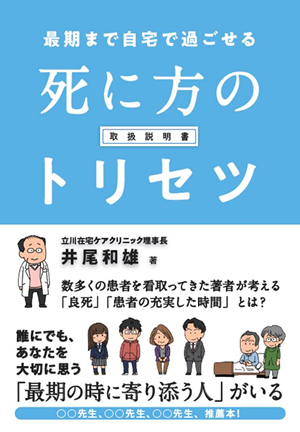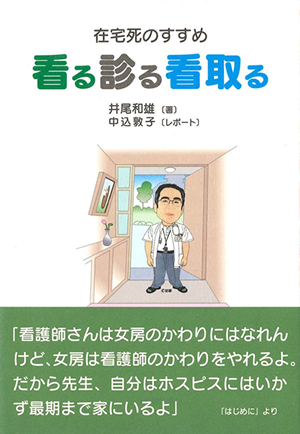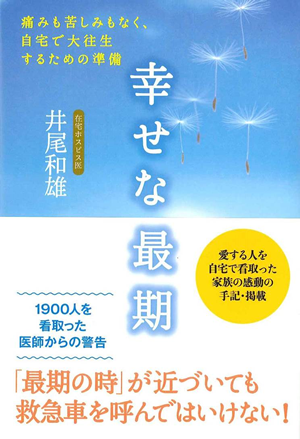理事長紹介
理事長ご挨拶 Greeting
開業の動機
開業の動機は熊本市で内科を開業していた父の肝がん死です。1995年1月17日の阪神淡路大震災の直前にインターン時代を過ごした病院で加療不能のまま数か月で寂しく、不憫な死を迎えました。緩和ケア後進国、死に場所も選べない国という事実に憤慨し、麻酔科医から緩和ケア医を目指す決心をしました。当初はホスピスを建てることを目標にアメリカ、日本のホスピスを見て歩きました。立川市にホスピスを建てることが決まりかけましたが地主の偏見「先生、そこは人の死ぬ場所だよね、親戚が……」で断念しました。そんな時当時の厚生省のアンケートが目に留まり、がんの末期になった時に過ごしたい場所に6割の人が自宅を挙げていることを知りました。「これだ!」、在宅の緩和ケアから始めることにしました。1996年に日本在宅ホスピス協会に登録、勉強を始めるとともに当時勤務していたレディースクリニックで在宅緩和ケア活動を開始しました。産婦人科ということで活動は広がらず、2000年2月に立川市に在宅緩和ケアを提供する在宅専門診療所を開業しました。

理事長 井尾 和雄
やっとここまで来た
立川市を中心とした半径16㎞、片道30分程度の多摩を訪問地域とし全域訪問の市町村は16ヶ所、一部訪問の市町村は10ヶ所で人口は300万人を超えます。
多摩にはがん診療連携拠点病院7ヶ所、東京都がん診療連携協力病院7ヶ所、緩和ケア病棟9ヶ所が存在しますが、住民は都内の国立がん研究センター、癌研有明病院、大学病院、有名大病院で治療を望み1時間以上かけて通院している現状があります。
開業当初は緩和ケア、ホスピスケアという言葉さえまだ聞きなれない、まして「在宅緩和ケア(ホスピスケア)?なんだそれ?」の時代でした。
普及のために①仲間つくり②病院医療者への周知③地域住民への周知の3つの作戦を立てました。
①在宅緩和ケアは多職種によるチームケアです。在宅ケアに携わる多職種連携「多摩在宅ケアネットワーク」、緩和ケアに従事する医師、看護師、薬剤師など連携「多摩緩和ケアネットワーク」、緩和ケアを学びたい医師、看護師、薬剤師のために1年間12講座の「多摩緩和ケア実践塾」を企画しました。訪問看護師、薬剤師、ケアマネ等への講演も行いました。
②病院長訪問、病院での講演、定期的ニュースレター、詳細な在宅ホスピス開始、終了報告書、病院連携医登録、懇親会・勉強会への参加、事務職の退院調整室訪問等を地道に行ってきました。
③丁寧な患者さん、家族への対応、遺族への十分なフォロー、遺族会の開催、市民講演会の開催、新聞・雑誌・テレビへの取材協力、3冊の本の出版、市民ボランティアの育成に努めてきました。
その甲斐あって信頼できる地域緩和ケアチームをでき、病院の理解も深まり、住民の理解も以前より深まったと感じています。
これからの課題
年度別看取り患者数(表1)をみると年々患者数は増加し2017年6月末の時点で在宅2715人、施設360人合計3075人の患者さんを地域で看取ってきました。
在宅看取りはがん87%、非がん13%の割合です。
紹介病院(表2)をみると立川市近隣の病院ほか都内のがん専門病院、大学病院、有名大病院が名を連ねます。治ることを夢みて病院を求めて彷徨い、加療不能で行き場を失い地元へ戻される東京の事情が見て取れます。
在宅看取り患者診療日数(表3)をみるとがんの場合1週間未満12.46%、1か月未満49.89%で亡くなっています。病院からの紹介が非常に遅く在宅を希望されても家に居る時間が短いことが分かります。非がんの場合には6ヶ月以上が40.52%で介護期間ががんの場合9.38%に較べると長期になることが分かります。
在宅看取り患者死亡時刻(表4)をみると、24時間すべての時間帯で亡くなっています。常勤医3人、非常勤医4人で日中、夜間、休日どの時間帯でも速やかに看取りのために緊急訪問します。国はかかりつけ医同志の連携で看取ることを推奨していますが外来時間帯、夜間、休日の急変、看取りに速やかに対応することは難しいと思われます。
2014年の立川の自宅死亡の現状(表5)を見てみると自宅死亡数288例の内133例(46%)はかかりつけ医により死亡診断書が出され、47例は当院で看取っています。残りの155例(54%)は検案事例になっています。155例の検案事例を見てみる半数近くが独居、発見が遅れた件数も42例と都会の事情が浮き彫りであると思われます。急死、外因死は122例(79%)ですが問題は残りの33例(21%)です。病名がついていた虚弱な高齢者に在宅医療の紹介がない、在宅医療、訪問看護が入っていたが看取っていないという事実です。(荘司輝昭院長がこの地域の監察医であることから全例調査しました。)新聞情報によると全国の大都市圏の事情は似たようなものです。
老老介護、認認介護、独居が増加し空き家が増加しているにも関わらず情報を出さない、検案事例が増えていることの情報を持たない、対策も打たない地元自治体に問題があります。また地元の医師会にも所属しない、責任感のない在宅医療、訪問看護が横行していることにも問題があります。
これから増え続ける、老老介護、認認介護、独居世帯ではがん難民、介護難民、看取り難民が続出します。地域総動員で体制を作ることが早急に求められているのが今です。当院は今まで以上に地域に貢献できるように努めて参ります。
経歴 Career
1952年熊本生まれ
学歴
職歴
所属学会
日本在宅医学会(在宅専門医)
日本ホスピス・在宅ケア研究会、日本在宅ホスピス協会
日本死の臨床研究会、日本在宅医療研究会 その他地域の在宅関連研究会多数
趣味
ゴルフ、映画、写真
学会発表・講義講演活動 Lecture
| 日付 | 講演テーマ | 主催先 |
| 2017年 | ||
| 9月23日 | 在宅ホスピスケアの普及は地域を変える~在宅ホスピス普及への取り組み~ | 日本在宅ホスピス協会 |
| 9月23日 | 診る、看る、看取る | 日本在宅ホスピス協会 |
| 9月17日 | 在宅医療の現場における患者の動向(抗がん剤治療との関連) | 日本在宅ホスピス協会 |
| 8月19日 | 『後悔しない最期の時の迎え方』 | 多摩らいふ倶楽部 |
| 8月16日 | 『後悔しない最期の時の迎え方』 | 多摩信用金庫本店「三水定期講演会」 |
| 5月17日 | 『後悔しない最期の時の迎え方』 | 多摩信用金庫本店「三水定期講演会」 |
| 4月20日 | 『地域包括ケアシステムの実現に向けて』~今、我々がやるべきこと~ | 多摩在宅ケアネットワーク |
| 3月11日 | 『人の繋がりはすべて縁』 | ボランティアさくら「結いの会」 |
| 2月15日 | 『後悔しない最期の時の迎え方』 | 多摩信用金庫本店「三水定期講演会」 |
| 2016年 | ||
| 11月16日 | 『後悔しない最期の時の迎え方』 | 多摩信用金庫本店「三水定期講演会」 |
| 11月1日 | 『麻酔科医から在宅緩和ケアを開業して15年今思うこと』 | 日本臨床麻酔学会 |
| 10月23日 | 『地域における在宅ホスピス専門チームの活動』 | 国際医療福祉大学 |
| 9月29日 | 『がん患者の在宅緩和ケアを考える』 | 災害医療センター |
| 9月21日 | 『後悔しない最期の時の迎え方』 | 多摩らいふ倶楽部 |
| 6月24日 | 『立川在宅ケアクリニック16年の歩み』~在宅ホスピスケア普及を目指して~ | 在宅医療推進のための会 |
| 6月18日 | 『最期は何処で』~自分らしい終章を求めて~ | 日本リビングウイル研究会 |
| 5月18日 | 『後悔しない最期の時の迎え方』 | 多摩信用金庫本店「三水定期講演会」 |
| 4月14日 | 『多摩地区の地域包括ケアシステムの現状』 | 多摩在宅ケアネットワーク |
| 3月13日 | 『実践的在宅ホスピスケア16年間の歩み』 | 塩野義製薬 |
| 3月12日 | 『都会における地域包括ケアシステムと在宅緩和ケア』 | 日本医療マネジメント学会 |
| 2月20日 | 『後悔しない最期の時の迎え方』 | 府中市「市民公開講座」 |
| 2015年 | ||
| 12月10日 | 『増え続ける独居世帯の医療・看護・介護の連携による在宅看取りを考える』 | 多摩在宅ケアネットワーク |
| 11月21日 | 『家に帰ろう』~幸せな最期~ | 久留米市「在宅医療市民公開講座」 |
| 10月17日 | 『地域包括ケアの中での緩和ケアについて』 | 多摩緩和ケアネットワーク |
| 9月12日 | 『地域包括ケアシステムの中で「最期まで家で支える」』 | 立川在宅ケアクリニック 市川Dr |
| 8月23日 | 『幸せな最期~後悔しない最期の時の迎え方~』 | ドリーミー |
| 8月6日 | 『地域での癌の看取りにおける診療所-訪問看護ステーション間の連携の手法と有用性』 | 立川在宅ケアクリニック 市川Dr |
| 7月19日 | 『がんの看取り』 | 第26回日本在宅医療学会学術集会 |
| 7月8日 | 『在宅ホスピス医が本音で語る』~おだやかな最期を迎えるための準備~ | 多摩信用金庫本店「市民公開講座」 |
| 6月3日 | 『在宅緩和ケアの実践と在宅看取り~地域包括ケアシステムの真の目的とは~』 | 立川相互病院 |
| 4月25日 | 『当院における在宅看取りと周辺訪問地域の在宅死の現状と諸問題について』 | 日本在宅医学会 荘司Dr |
| 4月9日 | 在宅緩和ケアからみた『在宅での看取り・死について』 | 多摩在宅ケアネットワーク |
| 1月14日 | 『地域包括ケアシステムの目的』 | 立川在宅ケアクリニック |
著書紹介 About the Author